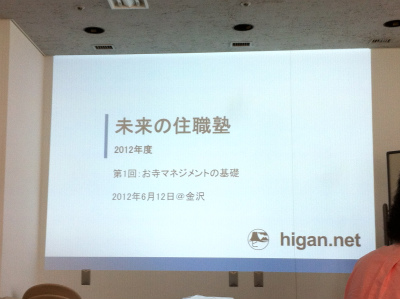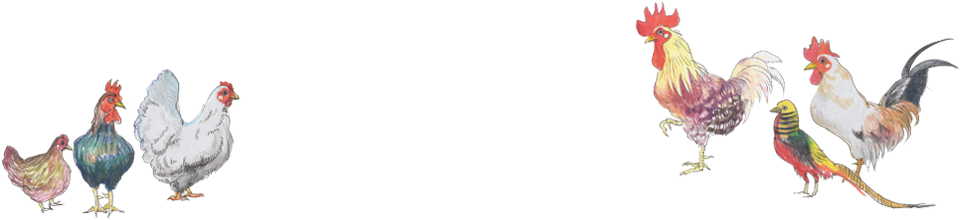これまでの活動や信念について語る松本師
昨日、帰真慶讃法要がお勤まりになりました。遠近各地より多数ご参拝いただき、ありがとうございました。実如上人から下付されたご絵像をお掛けして、皆様とともにお勤めした法要の後、松本紹圭さんのお話を伺いました。プロジェクターとスクリーンを使った視覚に訴えかける明瞭なお話と内容から「お寺を元気にしたい」という真摯な気持ちが伝わると同時に、僧侶である自分自身が問われる厳しさも感じました。
松本さんは、お母様のご実家のお寺で出遇った仏教の教えに魅かれ、僧侶を志しました。しかし、今の仏教界の状況をみて、もっと人々が参画できる大きな可能性を感じ、東京の都心ならではの環境を活かした活動を始められました。人とお寺をつなぐ仕掛けをさまざまな方法で具体化し、多くの人々に仏縁を結んでこられます。その体験から、 Continue reading '松本紹圭師来寺'»

左がしお糀 右がしょうゆ糀
福岡町地区の報恩講参りのとき、みそ糀店を経営しておられる「中田みそ糀店」さんで新商品の「塩糀」ならびに「醤油糀」をいただきました。手作りのお味噌を求めにこられるお客さんが今ブームの「塩糀」を買っていかれるそうです。このたび「醤油糀」というものも商品化されました。興味のある方はお店に行ってみてはいかが?遠方の方は発送もされていますので、問い合わせてみて下さい。
ちなみに「こうじ」の名は「かもす(醸す)」の名詞形「かもし」の転訛。漢字では「麹」「糀」とも書く。
だそうです。
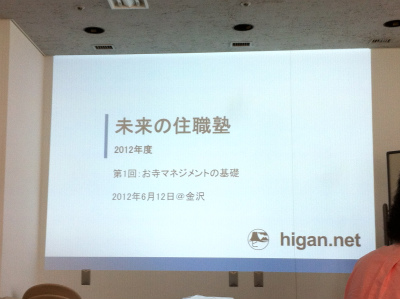
スクリーンに映し出された最初のタイトル
17日(日)に講師としてお招きの松本紹圭氏が主宰する「未来の住職塾」金沢会場に参加してきました。東京、京都、広島に続き、多くの受講希望者があったため、金沢でも開かれることになりました。
福井、石川、富山、岐阜と各地から各宗派のみなさんが受講され、第1回お寺のマネジメントの基礎について学んできました。
この年になって新たなことを学ぶのは非常に新鮮で、しかもこれまでの価値観や視点を問い直す良い機会でした。
自分が今、どこに立ち、何を目指していくのか、そんな思いをひとつひとつ整理していく…そしてそれぞれの形を具現化していく…そんな作業を志を同じくする人々と共に歩んでいくのがこの塾なのかなと思います。全6回、多くのことを学びたいと思います。

手水鉢にひろがる雨の波紋
しばらく続いた晴天も今日から雨模様となり、北陸地方は梅雨入りとなりました。畑で野菜を育てているみなさんにとっては恵みの雨でしょうし、寺でもゴーヤとヘチマを育てていますが、最近急に成長のスピードが上がってきました。40日間程続く梅雨は、じめじめとしてうっとうしい期間と思いがちですが、人間以外の動植物にはいのちを輝かせるうれしい活動期となります。そんな生き物を踏んで殺してしまうのは、私たち人間。お釈迦様は弟子たちにいのちを殺さないように雨期の間、出歩くことを制限して籠って修行することをされました。サンスクリット語で雨期を意味するvarsa(ヴァルシャ)を訳した安居(あんご)という期間です。雨を眺めながら仏典に親しむ日々を過ごしたいものです。

お講のお斎 ご馳走さまでした。
今年のお講はじめ、「親鸞聖人降誕会」がお勤まりになりました。今年は往生されてちょうど750年ですが、お生まれになってから839歳となります。若院が「五濁増のしるし」と題し、お話ししました。正像末和讃に「悲歎述懐和讃」という末法の世に生きる私たちの悲しむべき現実を述べられているものがあります。そのなかの
五濁増のしるしには
この世の道俗ことごとく
外儀は仏教のすがたにて
内心外道を帰敬せり
というご和讃があり、お釈迦様が入滅されてから時代を経ると、 Continue reading '二十八日講・親鸞聖人降誕会'»
 ニュース
|
ニュース
|  二十八日講, 五濁, 像法, 劫濁, 命濁, 悪世, 悲嘆述懐, 末法, 正像末, 正像末和讃, 正法, 煩悩濁, 衆生濁, 見濁, 親鸞聖人, 降誕会
二十八日講, 五濁, 像法, 劫濁, 命濁, 悪世, 悲嘆述懐, 末法, 正像末, 正像末和讃, 正法, 煩悩濁, 衆生濁, 見濁, 親鸞聖人, 降誕会