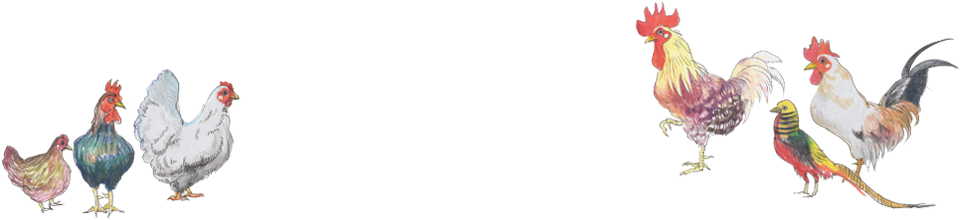阿弥陀堂での晨朝勤行(阿弥陀経)
14日(土)は、前の席を確保するため、何人かの方が、早朝、開門(午前5時)前にならんで下さり、中央最前列の席に座ることができました。深謝。おあさじ(晨朝)からたくさんの方がお参りになっており、阿弥陀堂から御影堂に移動するだけでも大混雑。底冷えする寒さの中、晨朝礼讃偈を味わいました。その後、10時からの日中法要まで、交代して朝食をいただき、始まるのを待ちました。全国各地から出勤の数百名の僧侶方と数千人の参拝者とともに宗祖讃仰作法(音楽法要)をお唱えして親鸞聖人のご和讃をいただきました。雅楽とシンセサイザーが見事に調和していて、唱えやすいお勤めでした。
法要後、飛雲閣と書院、唐門を案内しようと思いましたが、書院はお斎の接待のため、午後にならないと入れないとのことで断念。その後、普段は公開されていない「経蔵」を拝見。内部の構造は転輪蔵の回転式書架になっていて、非常に細かな細工が施されてありびっくりしました。それから門前町へ移動し、それぞれお土産物などを購入し、昼食会場へ。ゆっくりと料理をいただいたあと、最後に本願寺の南に位置する真宗興正派の本山、興正寺さんへ参拝。本願寺と興正寺は本願寺第8代蓮如上人の時代から一緒に歩んできた深い関係でしたが、明治時代に独立し、現在に至る歴史を少しお話しさせていただきました。なぜ本願寺と興正寺は並んで建っているのかということから、きちんと両寺の歴史を掘り起こす必要があると思います。そして龍谷大学大宮学舎を見学し、帰途につきました。

御影堂のお荘厳
今回の参拝を通して、50年に一度の法縁だから特別に考えるのではなく、常に願われている我が身であることを日々の生活の中で感じていくことこそが大切だと深く感じました。それがお念仏の教えですし、親鸞聖人が示された道です。そして真宗の教えは本願寺だけのものではなく、あらゆる人々に分け隔てなくつながる真理であるから、表面的なものにとらわれることから離れていく努力をしなければならないとも思いました。

数百人の奏楽員(雅楽を奏でる僧侶)

導師 大谷光淳新門さま

経蔵 第14代寂如宗主(1651-1725)が建立

興正寺から本願寺を望む
 ニュース
|
ニュース
|  唐門, 宗祖讃仰作法(音楽法要), 御影堂, 御正当, 日中法要, 晨朝, 書院, 経蔵, 興正寺, 蓮如, 阿弥陀堂, 飛雲閣
唐門, 宗祖讃仰作法(音楽法要), 御影堂, 御正当, 日中法要, 晨朝, 書院, 経蔵, 興正寺, 蓮如, 阿弥陀堂, 飛雲閣

総代さんから寄贈された安穏ひょうたん
今日、明日は善興寺の御正当です。9時30分からみんなでお参りをして親鸞聖人のお話を聞きました。その後、低学年と高学年に分かれて「真宗かるた」をして読み札に真剣に反応して盛り上がっていました。土曜学校からもたくさん応募しましたが、残念ながら採用はされませんでした。かるたが終わった後、庫裏へ移動し、修正会にお供えしたに餅を焼いていただきました。
11時からは小学生と入れ替わりで仏教婦人会の皆さんが参拝。正信偈行譜をお唱えし、団参で訪れた東山、吉水の草庵、元大谷のお話を若院から聞きました。お斎には、そば打ち名人の役員さ
んたちによるざるそばが振る舞われ、寒さの中で味わう打ち立てのそばに舌鼓を打っていただきました。お疲れさまでした。感謝申し上げます。
明日は、いよいよご命日です。午前9時半と午後1時半にお参りがあります。午前10時より本山の法要のインターネットライブ中継で参拝予定で、午後は「和讃の会」を開催致します。みなさまのご参拝お待ちしております。

白熱する真宗かるた

熱々のお餅をいただきました。

お下がりの手打ちそば

本願寺発祥の地元大谷(崇泰院)にある親鸞聖人の廟所跡
13日(金)〜14日(土)、かもん会で企画した「750回大遠忌御正当参拝ツアー」に行ってきました。初日は、東山の知恩院界隈を巡り、吉水の草庵跡(安養寺さんと法垂崫)と、かつて本願寺があった元大谷、出家得度された青蓮院、そして往生の地、角坊へ。最後に六角堂を参拝し、盛りだくさんの内容でしたが、親鸞聖人の歩まれた人生を改めて味わい直しました。特に法然聖人ゆかりの地と本願寺の歴史が整理できたのがありがたかったです。二年前から一般開放しているという元大谷(本願寺発祥の地)崇泰院は、現在浄土宗のお寺ですが、9割以上の参拝者は浄土真宗の関係者であり、もう少し整備して管理する必要がある重要な所だと思いました。本山参拝についてはまた、改めてアップしたいと思います。

法然聖人が唐の善導大師と夢の中で出遇われた法垂崫

本願寺派が定める往生の地、角坊の新築された還浄殿の欄間

承元の法難の後、吉水草庵跡を残すため慈鎮和尚慈円が創建した安養寺

ライトアップされた鐘楼
除夜会は午後10時半から始まり、寒い中大勢に方にお参りいただきました。続いて年明けとともに勤められる修正会。新たな年をお念仏とともに迎え、昨年の出来事を振り返り、無常と世間虚仮、火宅無常の世界について考えました。本年もよろしくお願い申し上げます。南無阿弥陀仏

初体験のおもちつき
毎年12月29日は、餅つきの日です。杵と臼を使って昔ながらの作り方で行うのですが、近年は量が減少傾向にあります。今年はスペシャルゲストとして、アメリカ人のALTのHiroさんが参加してくれました。もちつき初体験ということで興味津々。お父さんが日系の方ということもあり、幼少期にはよくお餅を食べたそうです。初めてにしてはなかなかのつき方でした。とくに昔レストランでパン生地をこねていた経験から、お餅を丸めるのが上手で驚きました。あずき、おろし、きなこ、こんぶ、まめなど、つきたてのおいしいお餅をお昼にいただき、ご本尊に供えのお餅が準備できました。

きれいに丸められたお餅